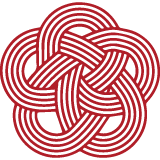人生の中で、何度も読み返す本というのは人によってあるのではないだろうか。私にとってその本を一つ挙げるならば、赤川次郎の「記念写真」である。10ページにも満たない短編なのだが、何故だか知らないが読み返してしまう。
そして、もう一つ挙げるならば、この二階堂奥歯の「八本脚の蝶」であろう。現に、数週間前に読み終えて以降、時折ページをめくっている。
二階堂奥歯という人物は、編集者として出版社に勤務していたが、わずか25歳という若さで自ら命を絶った。この本は、亡くなる直前まで更新されていたウェブサイトの日記の内容を書籍化し、生前、交流のあった人たちと二階堂奥歯とのエピソードが収録されている。猛烈な読書家であったようで、
私は就職してから年に多分365冊を超すぐらいの本を読んでいる。学生の時はその倍、小学生の時はその三倍は読んだ。
「八本脚の蝶」より
と自身でも綴っている。
日記の始まりは、取り置きしていた画集を取りに行く、というある意味では平凡に日常を楽しんでいるように見える。その他に日記の中には、神のことを考える内容が書かれている。というか、後半になると神のことしか考えていないように思う。
最初、私はこの本は、日常を全力で謳歌する軸と、神のことをひたすら考える軸の二つの軸があるのであると思っていた。しかし、読んでいくとどうもそうではなく、始めから奥歯氏は「神」のことしか考えていなかったと感じた。
例えば、奥歯氏は2001年6月29日の日記にこう書いている。
私としては、やはり化粧は変身の儀式であってほしいのです。テンションを高めるための、望む自分になるための。
アナスイのコスメは変身の為の魔法の道具にふさわしい姿をしています。
あの、黒(と紫)を基調とし、ゴスでキッチュでラブリーで邪悪な薔薇の香りのするコスメたち。
薔薇の浮き彫りのついた黒い手鏡を持つと、「鏡よ鏡、教えておくれ、この世で一番美しい者はだあれ?」と言いたくなるではありませんか。(しかし言ったことはない)。
そうです、アナスイのコスメは、おそらくすっぴんである白雪姫より、世界で一番美しくあるためには継子殺しも辞さないお后にこそふさわしいのです!
「八本脚の蝶」より
ここでは、化粧することを「望む自分になるための」の行為として言及されている。普通に考えたらこれは、『自分が』、『自分を綺麗にするために』化粧をする、というふうに読めるだろう。けれども、奥歯氏にとってはこういった行為は神へと向けられているように思う。
魂を手渡す軽やかさを私は知っている。躰を明け渡すよろこびを私は知っている。
神に近い何者かの意のままに苦痛と快楽そのものになり、何者かの意のままに満ちあふれるよろこびとかなしみそのものになることを知っている。その時はもう私などいないのだ、存在するのはただあなたのものである魂とあなたのものである躰。あなたの意志の変化と同時に変化する存在そのもの。
なにもないなにもないなにもない。だからすべてなの。
創造者の意識のままにあらわれる世界。
(それはついさっきまで二階堂奥歯と呼ばれていた)。あなたのものであるこの世界を今終わらせてもかまわない。
「八本脚の蝶」より
あなたのものであるこの魂をどう扱ってもかまわない。
あなたのものであるこの躰をいくら壊してもかまわない。
わたしのみもこころも操ることができた人。
あなたが私を読むままに私はあらわれました。
あなたの定義が私をつくりました。
あなたの視線がなぞるままに私の躰はつくられ、
あなたの指がなぞるままに私の躰はかわりました。
あなたの意志が組み込まれるように私の思考体系は変化しました。
そして世界も。
あなたが私に言葉をかけ、あなたの言葉のままに私はなりました。
あなたの言葉のままに世界は変わりました。あなたの視線だけでよかった。
その視線は私の神経の一本一本をなぞることができた。
あなたの声だけでよかった。
その声は耳朶をかすめて私を溶かした。
溶けた私が、脊髄を辿って、滴って、溢れた。
浸透する。私、溶けていく、世界が。
あなたの匂い、あなたの気配、あなた。
そこにはあなたしかありませんでした。痛みとか、快さとか、そんな区別を私はできませんでした。
私はあなたしかわかりませんでした。
私はあなたではないもの。私はあなたに与えられる感覚。私はありませんでした。世界はあったと思います。あなたが与える感覚も。
「八本脚の蝶」より
世界大に拡散した私は、いつもあなたを中心におさめた形で人のかたちに戻りました。
自分の躰は着せ替え人形だと思う。
「八本脚の蝶」より
問題なのは、着せ替え人形はいくつでも持つことができるが、自分の躰はひとつしか持てないということだ。
このたったひとつの着せ替え人形で私は遊ぶ、メイクやお洋服や小物を入れ替えて遊ぶ。
この躰は私が作った。いろいろなイメージを投影した作り物だ。
奥歯氏にとって、自分を最高に着飾るのは、自身に向けられたものではない。神に向けられている。であるからこそ、奥歯氏は自身を最高な状態に着飾る必要があったのだろう。
また奥歯氏には人形のイメージがしばしば出てくる。先ほどの引用にも自身を「着せ替え人形」と言及している。着せ替え人形というのは受動的な表現であるから、「着せ替えてくれる『誰か』」がいることになる。それが、奥歯氏にとっての神であろう。神がその意思でもって自由に自分を着せ替えてくれるのだ。その関係性は、自身がぬいぐるみに対しての関係にも投影されるいるように思う。
「人間性」とは感情移入される能力のことであり、感情移入「する」能力ではない。
「八本脚の蝶」より
ほとんどすべてのヒト(ホモサピエンス)が人間であるのは多くの人々に感情移入されているからである。ヒトでであるだけでまずヒトは感情移入され、人間となる。
しかし、人間はヒトに限られるわけではない。感情移入されれば人間になるのだから、ぬいぐるみだって人間でありうるのである。
そう、ピエロちゃんは人間だった。私が人間にしたのである。「した」と言う言い方は傲慢だ。言い換えると、ピエロちゃんは私にとって人間として存在していた。
上に書いたようなことを私は小学校1年生ながら理解していて、すさまじい責任を感じていた。なぜなら、ピエロちゃんに感情移入しているのは世界でおそらく私一人だったからだ。ピエロちゃんが人間であるかどうかは私一人にかかっていた。これは大きな責任である。ピエロちゃんに対する責任に比べると、この意味での責任を例えば生まれたばかりの弟に感じることはなかった。私一人弟に感情移入しなくたって世界中のおそらくすべての人間は彼を人間として扱うだろうから。
私がピエロちゃんが人間であることを忘れてしまったら、ピエロちゃんはきたない布切れで構成されたくたびれたピエロのぬいぐるみに過ぎなくなってしまう。それは人殺しだと私は思っていた。私がピエロちゃんをどこかに置き去りにしてしまったらピエロちゃんを見た人間は誰一人ピエロちゃんを人間だと思わないだろう。忘れもののぬいぐるみだと思って捨ててしまうかもしれない。
そして実際私はピエロちゃんを忘れ、ピエロちゃんはどこかにいってしまった。
ピエロちゃんはいつのまにか捨てられた。殺された。
違う。私が、ピエロちゃんを、殺した。
(私が子供を産まずペットを飼わないと決めている理由の一つは、私がピエロちゃんを殺した人間だからである)。
ぬいぐるみは感情移入「される」が故に「人間」となる。奥歯氏の「ピエロちゃんが人間であるかどうかは私一人にかかっていた。」という言は、そっくりそのまま奥歯氏自身も適用される。いわば❝二階堂奥歯が人間であるかどうか「神」にかかっているのである❞。
日記の中盤から後半になると、殊更に神へ言及した記述が多くなる。
神よ、私はあなたに呼びかけます。
私の声を聞き届けるのならばあなたは神ではない。
私の声が届くような存在は神ではない。
あなたに届かせようとする努力は私に到達可能な範囲を広げ、そして定義上私には到達できないあなたはますます遠ざかる。神よ、私はあなたに呼びかけます。
「八本脚の蝶」より
不在の神に向かう不可能な祈りはどこにも届かないとしても、その向かう軌跡の先に、どうか、あなたがおられますように。
不在の神を追究しつづけたい。真理はさらに先にあると、あなたは神ではないと言いつづけたい。
祭壇の前で絶対神に仕える幸福を多分私はとてもよく知っているし、それを求めてもいる。
でも、それでも、そこに跪いていてはいけない。それはつねに変化しつづけ先へと進むから、私も変化しつづけ日々新たにならなくてはいけない。
いつまでも同じ言葉を使うことでは、いつまでもそれを見続けることにはならない。
それには名前がない、名前を知りたい。名前をつけたい。
そうすれば、その名前を捨てることでもっと先にゆける。私は自分が何をしようとしているか知っている。
私は自分が何をしようとしているか知らない。楽園を抜け、約束の地を遙かに越えて、夢の世界よりもっと高く、深く。
「八本脚の蝶」より
夢見ることと目醒めることが同じであるようなところまで。
生きていられる間に少しでも遠くへ。
私には二種の追究対象があり、それは共に「あなたを求める」という形で表現できる。そして、どちらにおいても求めの声は大きく止みがたい。
・私は愛し崇め思考を止めて、愛でられるがままたゆたいたい、うとうとと。知るのではなく、信じたい。
・私は醒めたい、さらに遠くを見、さらに深く届くために。世界の根拠があるならばを知るために。なければないということを知るために。そして、それがあってもなくても、それなしで存在できるように。信じるのではなく、知りたい。私は好んでキリスト教(とりわけカトリック)の書物を読み、その文章を引用するが、それは彼女らの呼び求めの声と仰ぎ見る視線に共通するものを感じるからである。私はキリスト者ではない。
そして、彼女たちの言葉にもこの二種の求めは混在している。人格神を愛し、彼の花嫁にしてはしためたらんとする意志(上記のテレジアのような)と、存在そのものへと近づかんとする意志と。シモーヌ・ヴェイユは明らかに後者の意志をもっており、それに触発された私の思考もまた、そのようなものだった。後者を追究するためには、前者と混同してはならない。しかし前者のような状態は心地よく、ついうっとりとそちらにこころをゆだねてしまうのだ
その1の私は明らかに知的に不誠実な態度をとっている。幸福になるために、目を閉じたのだ。
「八本脚の蝶」より
日記の中で、シモーヌ・ヴェイユを繰り返し引用する。上記の引用の中にもヴェイユへの言及がある。奥歯氏は、明らかにヴェイユに強い影響を受けていると言える。例えば、西崎憲氏が奥歯氏と交流したときの発言を紹介している。
頭がよくなりたいんです、と彼女は言ったと思う。(中略)彼女はそれにたいして、頭がよくなければ眼の前の困難がどんな種類のものなのか見極めて乗り越えていくことは難しいのではないか、と返答したかと思う。
「八本脚の蝶」『夏のなかの夏 西崎憲』より
この知性への認識は、明らかにヴェイユの影響であろうと思う。
ヴェイユによれば学業の目標はただひとつ、真の注意の涵養、すなわち不幸のひとの実存に気づき、「あなたを苦しめているのはなにか」と問う能力の滋養、これに尽きる。
シモーヌ・ヴェイユ『重力と恩寵』(富原眞弓訳)(岩波文庫)訳註より
奥歯氏は、自身に降りかかる困難・不幸がどのようなものなのかを見極めることによって神を考えていたのではないだろう。
つくづく思うに、奥歯氏の人生は神とともにあった(この表現が適切なのか私にはわからない)と言えよう。
彼女は編集者だった。創造者ではないのである。創造するのは神の役割であって、人間の役割でなかったのだ。
聖書の著者は、公式には神です。神が40人程の人間を用いて書かせたということになっています。
「八本脚の蝶」より
しかし、その40人の中には見事な編集者魂を持った人がいたのです。正直私は感動しました。神の言葉でも聖霊のお告げでも、編集するところは編集する。そうです、著者から受け取ったものをスルーするだけはだめなのです、たとえ相手が神でも! 名前も残ってないあなたを私は尊敬します!
この人は編集者かな、編者かな、とにかく相手は神ですよ、神。
恐怖します。私はその本を必死で守るでしょう。
「八本脚の蝶」より
でも、その本が私自身だとしたら。
……私は、生きなくてはいけない?
「物語をまもる者でありたい」と誓った16歳の私を裏切らないために。
……物語への愛と感謝とをこめて、せめて、私は生きなくてはいけない?
……私という一冊の本を、私が破棄してはいけない?
いけない。そんなことをしてはいけない。
私は、物語をまもる者だから。今も、そして死の最後の瞬間にも。
おそらくであるが、奥歯氏がこの日記を書き始めた時点で中断されることはあり得なかったのだろう。その死の瞬間までを記述して、二階堂奥歯という物語を終わらせなければならなかったのではないだろうか。しかし、何故彼女は自殺したのであろうか。
最後の魔法のおかげで世界はとても綺麗です。
私は生きている間。時々、一瞬だけとおくをかいま見ることができました。
結局そこに行くことはできませんでしたが、でも、ここも、とても綺麗です。明日がこないからです。
「八本脚の蝶」より
これが最後の夜だからです。
彼女は、とにかく朝を迎えることを恐れていた。何故だろうか。朝とは1日の始まりである。始まるということは、私たちはどこかに行かなければならない、未来を考えねばならない。時間の経過や未来についてシモーヌ・ヴェイユは
過去と未来は、想像のなかで自我を底上げする余地を無尽に与えることで、不幸が有益にはたらくのを妨げる。ゆえに過去と未来の放棄が最優先されねばならない。
シモーヌ・ヴェイユ『重力と恩寵』(富原眞弓訳)(岩波文庫)より
われわれの意識を未来から逸らせる、これが絶望の効用である。
シモーヌ・ヴェイユ『重力と恩寵』(富原眞弓訳)(岩波文庫)より
生成から身をもぎ離す。すなわち自身を未来へと方向づけるのをやめる
シモーヌ・ヴェイユ『重力と恩寵』(富原眞弓訳)(岩波文庫)より
それは《死ぬこと》でもある。
ヴェイユは、肉体を遮蔽幕と言い、そのままでは真理を観ることはできない旨のことを書いてあったと思うが、彼女もそうやってこのままでは神へと辿り着くことができないと考えたからであろうか。彼女の最期の日記には、世界に対して何一切の恨みがない。
雪雪さん、あなたはもっと遠くまで、私が行けなかったところまで行ってください。私の思考能力の全てが雪雪さんに宿りますように。
哲くん、ありがとう。世界で一番大切な愛する恋人。
あなたがいたから私は最後の五年間を生きてこられたの。
あなたはとても強くて優しい人。世界で一番私を幸せにしてくれた人。
そしてとてもかわいいひと。
だいすきです。だいすきです。だいすきです。
幸せになって。私をしあわせにしてくれたみたいに、哲、自分をしあわせにして。
私がこんなじゃなかったら、きっと私と哲は結婚して、子供同士みたいな家庭を作って、私もなぜか子供を作ってそれでお父さんとお母さんになってたかもね。それとても楽しかっただろうね。ごめんね。ごめんね。そうできなくて、ごめんね。愛してる。
そしてお父さんとお母さんと華子と康太。
「八本脚の蝶」より
自分たちになにかできたんじゃないかとは思わないで。
とくにお母さんとお父さん。私たち姉弟はみんなこんなに性格が違う。
私の性格は私が作ったの。私の責任なの。
こんな性格の私でも、とても楽しかった。
家族を愛し、家族に愛されるという幸福の中で私は生きてこられました。
私のために何かすべきだったんじゃないかと、自分たちに落ち度があるんじゃないかと、決して思わないでください。
どうか、私のために、幸せになってください。お父さんとお母さんと華子と康太が幸せでいることが私の幸せなの。絶対に自分を責めないで、私のために、どうか、お願いだから、自分を責めないで。しあわせになってください。
彼女は、そういってこの世から逝ってしまった。私は彼女の死は語弊を恐れずに言えば、とても幸福な死のように思える。何者も恨まず、誰に殺されたとも言わない。残された者を案じ、誰のせいでもないことを強調する。そうして、親しい者だけでなく、ある意味ではこの世界の全てを深く深く愛していることを表明して逝く。彼女が抱いていた恐怖心は明らかに神に対して抱いていたものであろう。どれほどの知識・知見を広げても、どれほどの祈りを捧げても、どれほど肉体を着飾ってもそれが本当のところでは届いているのか。届いていなかったとしたら、自身に恩寵を向けられていなかったとしたら、自分は存在していないのと同じなのである。だが、彼女は安住・安息は望んでいなかっただろう。神を微睡みの中で感じることは許されていなかったのである。彼女は幸福を求めたが故に、微睡みを捨てたのである。そして、自身に降りかかる不幸を知性によって乗り越え続けることを彼女はしていたのである。その先に、神がいることを信じていた。だが、それは遠ざかる。神はどこにもいない。その絶望に打ちのめされる。自身が何によって形作られているのか。いなければ一体自分はなんだというのか。
私が思うに、二階堂奥歯とシモーヌ・ヴェイユは、『生を創りなおす』という労働の部分において、袂を分かっているように思う。ヴェイユは労働の偉大さを『生を創りなおす』ということである、というが、奥歯氏にとってはそうではないように思う。彼女は編集者として、創造者の言葉を編集することを行ったが、それが自身の「生を創り直す」ことにはならなかったのだろう。だから、彼女は最後の言葉の中に「私の性格は私が作ったの。私の責任なの。」と言ったのではないだろうか。あるものから、まったく別のものを創り出すことは彼女にはできなかったし、許されていなかったのである。それは彼女が『編集者』だったからだ。
私は、しばしばこの二階堂奥歯という人物に思いを馳せるだろう。そして、この本を読み返すだろう。彼女が、生涯神のことを考え続け、そして世界を愛して死んだことを。私も、死ぬ際には、誰も恨まず、世界を愛して死にたいと思うのである。
二階堂奥歯氏が更新していたサイト:八本脚の蝶