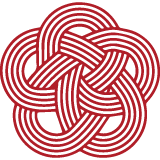この本は、第155回芥川賞を受賞した作品で、私が読もうと思ったきっかけは、人から勧められたから、であった。
主人公は、世間の感覚とはどこかずれた感覚を幼い頃から持っている。
例えば幼少の頃、公園で死んでいた小鳥を『世間』は「お墓を作ろう」と言ったが、主人公は「焼き鳥にしよう」と提案した。
また他には、小学校時代に男子同士の喧嘩が起こった際は、主人公はスコップで男子の頭を殴り喧嘩を止めた。
それが何故ダメなのかを主人公はまったく理解ができなかったのである。上記のことは、主人公の性格や思考を伝えるエピソードとして紹介されているがまったく重々しさを感じないような描写がなされている。主人公を通してエピソードが語られているからだろうか。深刻である「はず」のことも、どこ吹く風のように、逆に『世間』の方が得体の知れないことを言っているかのようにも感じられた。
その後、主人公は「皆の真似をするか、誰かの指示に従うか、どちらかにして、自ら動くのは一切やめ」る、という処世術を使って人生を過ごすことを決める。自分で行動しなくなったことでトラブルはなくなったが、必要なこと以外は話さなくなったことで逆に『世間』からの心配を買った。
そんなときに、主人公は「コンビニ」と出会う。主人公はコンビニ店員として働くことで、初めて世界との『正常な』接点を手に入れる。
そこから主人公は、「コンビニ店員」としての生活を18年間も続けることになる。この生活に主人公は何も不自由さを感じていない。
「朝になれば、また私は店員になり、世界の歯車になれる。そのことだけが、私を正常な人間にしているのだった」
「外から人が入ってくるチャイム音が、教会の鐘の音に聞こえる。ドアをあければ、光の箱が私を待っている。いつも回転し続ける、ゆるぎない正常な世界。私は、この光に満ちた箱の中の世界を信じている。」
コンビニにいることだけが、主人公を「正常な人間」にしているのである。
そんなときに、主人公は白羽という人間と出会う。『世間』が自分の人生に土足で足を踏み入れてくることを嫌い、「機能不全世界」と世間を罵り愚痴を吐く男である。主人公は、この男と奇妙な同棲生活を過ごすことになる。男っ気のない主人公にとって、『男と住んでいる』という事実は『世間』を驚かせ祝福を受けた。その方が、主人公にとって都合がよかったのである。学生時代の友人、妹、職場の人間に至るまで興味津々に内情を聞いてきたのだった。特に主人公は、店長や同僚がそういったことを聞いてくることについて「不協和音」と称した。主人公にとって、入口の開くチャイムの電子音や、「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」という形式ばった掛け声、レジでスキャンする機械音が協和音だったのである。
その後主人公は、あることがあって18年間勤めたコンビニを辞めて新しい仕事を探すことになる。辞めた後の主人公の生活は廃人のようになった。自身の生活の基準が「コンビニのため」だったので、眠ることにすら何のためなのかわからなくなった。昔、私は「仕事が人生の全てだ、と思っていた人間が定年退職後うつになった」という話を聞いたことがあるが、主人公もそれに近いように思う。
コンビニを辞めて1か月ほどした時に、仕事の面接のために主人公は外出した。その出先でコンビニに立ち寄った際に、主人公はあろうことか店の品出しなどをし始めたのである。主人公はそれを「コンビニの声」と称し、コンビニがなりたい姿にしているだけだというのである。主人公は「私はこの声を聴くために生まれてきた」といい、「気が付いたんです。私は人間である以上にコンビニ店員なんです」と同行している白羽に告白した。そして、主人公は窓ガラスに映った自分を見て「初めて、意味のある生き物に思えた」と感じて物語が終わる。
私は、この小説全体を通して重々しさをまるで感じなかった。主人公が、男子をスコップで殴ることも、コンビニを辞めてからの廃人の描写も、途中妹が姉である主人公の異常さに泣きじゃくる姿も、本来は深刻であるはずのことも重々しく描かれていないように思う。それは、主人公からの視線で物語が語れているからかもしれない。歯車、一つの部品を見るような視線で見ているように思う。❝小鳥が死んだらみんなで悲しんでお墓を作る❞、❝男子同士が喧嘩をしたら皆で非暴力で止めて先生が来るまで待つ❞、❝大学を卒業したら会社員として働く❞、❝30代ぐらいになったら恋愛結婚をし子供を育てる❞、その『世間』でいうところのものが、私たちが普段考えているであろうコンビニなのである。定式化された機械的に動く世界。主人公がコンビニを「水槽」と表現しているところがあるが、主人公にとっては『世間』が一つの大きな水槽入れられた無機質な世界なのである。主人公は、コンビニという生々しい『社会』の中で、無機質な『世間』を眺めているのである。この本は『現代の実存を軽やかに問う』というふうに紹介がされているが、『もっと人間らしい生き方』をした方がいいのではないか、と私たちが疑問を呈しても、主人公はなおのこと「コンビニ店員」として生きることこそが自身の実存であり「もっとも自分が意味のある生き方である」と反芻されて終わるだろう。逆に、「もっと人間らしい生き方」を主張した側が、いわば主人公を『社会の歯車』にしてくる存在として『実存を奪う存在』として現れてくるのである。
この本は、正常・異常、生々しさと無機質さなどが、容易に揺らいでしまうことを描いている本でもあるように思う。生々しい生を主張しようとすればするほどに、どこか無機質な形式化されたものへとなっていき、逆に無機質な社会であるように思われるところに全身全霊で身を置けば置くほどに、生の生々しさが現れてくるのである。